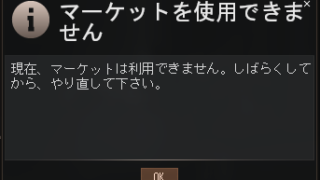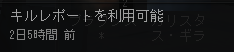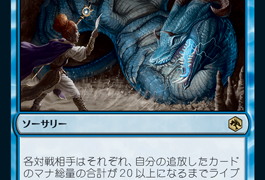Contents
第二章 ノット・ジーニアス
マイナと行動するようになって、一ヶ月が経とうとしていた。
広いフィールドを、移動用の電動バイクが駆けていく。
俺とマイナでそれぞれ二両ずつ。襲撃に備えて、ほどほどに並走の距離は置いてある。
ボイスチャットをしながら、狩り場の活火山へと向かっているのだった。
いろいろ話していると、罪悪感が芽生えてきた。けっこうな嘘で覆い隠した経歴の少しくらい、取っ払ったほうが良いだろうか?
「ユウトお兄さんって優秀だね。昔、親が私に雇った、東大生の家庭教師みたい」
「へえ……東大、東京大学か」
案外、良いところのお嬢様なのか? とも思ったが。
なんだかんだ、マンツーマンで教える家庭教師――コミュニケーションのできる人間は淘汰(とうた)されずに職業として現代でも成立している。
「受験に落ちたのか?」
「うん、頑張ったんだけどね。
東大は難しかったのでやんす」
あ、ストレートにお嬢様だ。
「で、第二志望にすらも行く気を失くして『グッバイ』に参加した、と」
「私の心を見透かすなー!!」
心臓を抱えるようなポーズをして、マイナが言った。
どうやら、図星だったらしい。言ってみるもんだ。
「俺も、……東大を目指した時期があるんだ」
「んで、受験に落ちてやる気を失くして、『グッバイ』を始めたの?」
マイナは、同じような言葉で対抗してくる。まだ、甘いね。現実の酸っぱさも分かっていないとみた。人によっては、一生知らなくても良いものでもあるが。
「……合格はできたんだ」
「うげげっ! 凄いじゃない!!」
俺は少し溜息を吐(つ)いてから、つらい記憶を掘り起こす。
いや、掘り起こすまでもない。焼き付いた感覚で、フラッシュバックが起きるだけだ。
「進学校だったから、優秀な奴らは多かったんだよ。
俺は『ガリ勉グループその一、その二、その三』のどれかの、筆頭格みたいな奴だった。
当たり前のように一日のほとんどの時間は、受験勉強。高校三年生のときなんて、この『グッバイ』以上に頑張っていたかもな。
ただ、何人か。ろくに勉強をしている素振りもないのに、合格するやつらも居たんだ」
「……」
マイナは、小さく唸った。声にならない声、というやつだ。
俺でも、何も知らない頃にこんな話を聞かされれば、同じような反応を示すだろう。
「極めつけは、一年遅れの浪人をした後に入ってきたやつ。
聞いた話じゃ、遊びに遊んで、受験勉強は二ヶ月で合格したらしい。そりゃ、下地はあったんだろうけど」
「天才?」
「天才は多いさ。
『東大以外はゴミ』って思っている連中は、未だに多いからなあ。
あるいは海外の、東大より格付けランクが上の大学を目指すような怪物も、居ないわけじゃないし。まあ、……俺は数学が好きだったから、数学科を目指していたんだが、受験数学と大学数学はまるで別物でね……。
二年生の途中で、退学届を出したよ」
「ザ・挫折って感じ?」
俺は頷いた。全く、その通りだ。
「まあ、天才なんてどこの分野にもいるだろ。僅かな努力で、全てを握るようなやつ。
勉強、投資、経営、ゲームだってそうだ」
「『グッバイ』も、コミュ力の鬼みたいなのが、超デカい組織を運営しているでしょうねー」
「コミュ力以前に、マルチリンガルだからな。日本語の習得は特に難しいだろうが、最低でも英語力は必須だろう、とは……。
まあ、ソロで求められる才能なら、やっぱり投資家だな。
それと強さを求める求道者プレイなら、対人戦専門のプレイヤーってのもある」
「PvPヤーね。
そういや、この前のダンジョンにいた綺麗な女の人も、そうだったのかしら」
マイナもその姿を見ていたらしい。少女のマイナから見ても綺麗に映っていた人物のようだ。
「わからない。
場馴れしていそうではあったけどな……直感だけど、運動神経が良いタイプだな。脳と肉体の、なんというか神経系の接続率が妙に高いやつっているよな」
「『頭が良い』って。一言でまとめちゃえば?」
マイナは、バッサリと要点を押さえて済ませてしまう。シンプルだ。
確かに、考え過ぎていたかもしれないな……。
俺は微笑みと、それを含んだ声で応じた。
「IQだけじゃない、アスリート的な頭の良さだな……。
一瞬しか見ていないが、あれは難敵だ。俺の、天才に多少は出会ってきた人生経験が、激しく危険だと叫んでいるからな」
「ずいぶん、高く買うのね。私はどれくらいなの?」
「期待の成長株だ。
……今は安い」
「ぶーぶー!!」と、ぶーたれだしたマイナには、
「今が買いのチャンスってことさ」
と言ってやる気を繋いで、場を盛り上げておく。
「人間は、証券にはなりませぬ」
せめてもの反撃らしい。ま、人の価値が株式として分割されて、普通に売買されるようになったら、いよいよこの世の終わりだろうな。
……証券化されるのは、会社までにしてくれ。
火山の麓(ふもと)に付いた。頭を痛くなるくらいに見上げれば、黒い煙を吹き出す山頂が見える。この先は、山林部となっていく。
かなり価格の安い移動アイテムのバイクはここで乗り捨て、回収はしない。
ここからは、徒歩での移動となる。
「山(やっま)のっぼりー、ハッイキングー、ひっとごろしー♪」どちらかというと、賊のバイキングなんだけどな。
浮かれて屈伸しているマイナはさておき、ここは低セキュリティエリアとなる。いくらでもPKが可能な場所で、ペナルティなんてものは金(G)や時間の経過で解決できる程度。非常に甘い。マイナにも知らせてあるのだが、今回は全滅の可能性も織り込み済みの、低予算パーティとなっている。
カモ狩りができればそうするが、かなり真面目な戦闘とか、運が悪ければ数十人数百人に待ち伏せ、ないし遭遇戦となってあっけなく全滅か、なぶり殺しに遭う可能性もある。
俺たちの装備は、火力・攻撃能力に偏(かたよ)らせた構成。
その入手が危険であるがゆえに市場に流れ辛い、従って高価な探索アイテムなどを回収する余裕はあまりない。
あくまでもお互いに、危険地帯の渡り歩き方を実戦で学ぼう、という体裁になる。
俺とマイナは取り回しの良い、お揃いの実体弾式のサブマシンガンを主武装としている。拳銃を一回り大きくした程度の、小型・携行式機関銃だ。
副武装として使われやすい小型携行火器でもあるが、山林・山岳地帯では動きやすくて助かる。さらに、発砲音がほぼしなくなる、消音器(サウンド・サプレッサー)を銃身の先に装着・カスタマイズしてある。
弾頭は四.六ミリ口径(太さ)と最小クラスだが、高初速で発射される弾丸は、威力・貫通力共に、悪くはない。近距離で弾幕を浴びせるには、非常に適している。
もっとも、およそ二.五秒で一弾倉の三〇発を撃ち切って弾切れになる。
再装填する余裕はあるのかわからないため、襲撃には準備・タイミングが重要だ。
反撃をなるべく避けるために索敵と待ち伏せを実行し、そして一方的に皆殺しにする……できるといいなー、といった感じだ。
そのはずなのだが。
「実際のところは、退屈さとの勝負なんだよな」
「うん。緊張する上に、暇とは……」
俺とマイナは、お互いに小声でコンタクトを取る。
敵なり、カモなりが居なければ当然、緊張感があるだけのただの山の遠足・散策で終わってしまう。かといって、低セキュリティエリアで油断をするわけにもいかない。仕方がない。
パブリックな『グッバイ』のゲーム掲示板を見るに、この付近のプレイヤー活動――PKが活発化しているのは明白だったので、茂みを抜けていく先でいつ戦闘になるかは分からなかったのだが……。
もう一つの主武装の、握り棒(グリップ)から光の刀身を展開できる、ほぼ無音の光剣(ライトセーバー)で雑魚NPC狩りを行う。背後から速やかに始末して、進行方向を確保するのだ。
よく出没するのは、亜人や四足獣の害獣、といった類のクリーチャーになる。
火山ということも関係しているのか、ドラゴン系統のクリーチャーがボス格の敵として出ることもある。倒せば美味しい報酬が手に入ることが多いのだが、危険地帯で激しい戦闘を無闇にしていると、いつPvP・PKに発展するかわからない。
横槍を入れられる程度では済まされないのだ。
PvPは、なにが起こるかわからない。突発的、という言葉が一番よく似合う。
ただの採集装備のカモを簡単にキルできることもあれば、カモと思ったそれは実は餌で、そのさらに外周で待ち伏せていた複数プレイヤーから攻撃を加えられる、とかもある。
正々堂々の決闘、などは決闘システムを使ったり、コーポに宣戦布告したりする、くらいしかない。また、前者の決闘ははっきりとしているが、後者は血みどろの利権闘争に発展しかねない。まあ、武器弾薬の値上がりは正直、商人としては願ったり叶ったりなのだが……。
アイテム収集をしているプレイヤーをキルしてアイテムを奪えば、それは擬似的な収集活動となる。採掘などをさんざんしたプレイヤーが、最後にたんまりと荷物を抱えて移動しているのを狩れば良い。
残酷な話だが、そもそも危険地帯に行くというのはそういうことで、PKされて泣き言を言う人間はあまりにも覚悟が足りない。
ただし、いくらかっこつけてみたところで、他のプレイヤーが居ないのはどうしようもない。
「あ、宝箱(クレート)」
マイナが指差しをした先には、かなり遠巻きに――五、六〇メートルは先だろうか、よく見つけたものだ――自然感溢れる山林部には似つかわしくない、無機質なアイテム・クレートが在った。
「まずい」
俺は、宝箱に目掛けて今にも木々の間から飛び出しそうなマイナを俺は、彼女の正面に差し出した腕と手で制する。
不満の声を漏らしそうなマイナをさらに小声で制し、動きを止めさせる。
「狩られるぞ」
「……危険なの?」
「ああ。
おそらくは意図的に残している。クレートはそのまま、プレイヤーの死体と同じ意味を持つからな」
中身のなくなったクレートは、一定時間の経過で消滅するが、アイテムが少しでもクレート内に残っていた場合は、空のクレートよりも自然消滅に時間がかかる。
そのため、PK後は換金性の高い、軽くて高価なアイテムだけを抜き取る。
クレートに引き寄せられた他のプレイヤーをキルして、さらにクレートが出来上がる、という寸法。その可能性が高かったのだった。
右奥の茂みから姿を出した、男性の見た目をしたプレイヤーが、クレートの前に歩み寄ってきていた。
「あ、他のプレイヤー。ちょっと。取られちゃう」
「いや、死ぬ」
俺は冷淡に、そう断言した。待ち伏せがありそうだし、そしてなによりも俺たちが待ち伏せをしているから、どうあがいてもこのプレイヤーはキルされるはずだ。
マイナと同じ考えのプレイヤーが出てきたわけだ。装備の見た目からは、ソロの採集・PvEプレイヤーだと判別できる。
遠くから伸びた光線が、彼の胸から頭部にかけて照射される。血すら焼き焦がす一撃。
ワンキル。
左側、前方。百か二百メートルほど先からの狙撃。
威力が高く、音は消音銃ほどではないがあまり発生しない、レーザー・ライフルだった。
「なるほど、あそこが狙撃位置か」
俺が判断すると、
「あそこだ!! 追いかけろ!!」
野太い男の声が聞こえた。
男女、合わせて五人のパーティが、先ほど撃たれたプレイヤーが出てきた茂みから飛び出し、樹木を遮蔽物(しゃへいぶつ)としながら、狙撃手へと距離を詰めていく。
「PKK(プレイヤー・キラー・キラー)、ってところか」
「コーポ?」
「前に同じようにキルされたことで、この狙撃手(スナイパー)に恨みでもあるんじゃないのか。
最近のキルは同じようなやり口が多いと聞いたし、同一犯かもな。
……なるべくバレないように、追いかけてみるか。なんか、楽しそうだ」
「アイアイサー!」
PKK勢が走って進み終え、ある程度距離が置かれるのをしばらく待って、俺たちも置い賭け始めた。
「やっとPvPだな」
「うわー、楽しみでやんすー」
語尾は無視するとして、身軽な装備の俺たちは少しずつ五人組の後を付け狙って追いかけていく。既にレーザー・ライフルでキルされて、三人組になっているのだが、まあいいか。
「あれ? あのプレイヤーじゃね?」
「あ、そうかも」
黒の長髪に、今回は緑色の迷彩スーツ。以前迷宮孔で出会った女性プレイヤーに見えたのだが……。
「ちょい待ち」
銃声が鳴り響く中でマイナを呼びつけた俺は、草木が良く生い茂った、大きめの木の陰に隠れる。遮蔽物(しゃへいぶつ)としては申し分ないだろう。
「コンタクト情報を確認。プレイヤー名『SUZAKU(スザク)』。
やっぱり、あの時と同じプレイヤーだったな」
システム上、同じエリアで出会ったことがあるか、戦闘したことのあるプレイヤーは、接触記録(ログ)が残る。そのため、PK可能エリア内の悪名高いプレイヤーには、報酬金(バウンティ)付きで指名手配されることもある。
スザクは、自身の正面にエネルギー式の単一指向性アーマー――いわゆるバリア――を展開し、高周波ブレードの刃をもつ刀(カタナ)を振り回し、残る三人をキルしに来ていた。
「スザクってプレイヤー、右肩にキルカウントの数字が出るようにしているんだ。背中にも確認」
「うへー、一〇〇〇人超えそう……」
キルした人数がそのまま英数字で背番号として表示される。
ダサいように見えるが、偽装不可能なシステム上では実際、脅威にしか見えない。
仲間同士で殺し合って、こけおどしの数を増やすという、発想が貧困な輩も居るのだが――まともな実績を持っている場合もままある。
「うわ、全員キルされちゃった」
「凄腕過ぎる」
あっけにとられるマイナと、唸る俺。
「……仕掛けるぞ」
今のスザクはブレードを鞘に納め、後ろを向いて傷の治療をしていた。ナノマシン・リペアキットによる急速回復だ。
「ええ……!」
「もとから、こういう戦いがしたかったんだ。付いてこい」
茂みから茂みへ移動し、俺は姿を現して、二、三〇メートルほど先のスザクに向けて発砲。
ほぼ無音の、トイガンにも満たないようなサブマシンガンの作動音と、高速貫通特化型の弾丸(バレット)がスザクへと猛撃を仕掛けていく。
ヘッドショットを狙ったが、たまたま屈まれて回避された。……たまたま……か?
マイナと共に、スザクの胴体や手足に次々と着弾する、サブマシンガンから発射される拳銃弾。
スザクが横転し、反撃体勢を整える頃には、弾切れ。俺は「マイナはリロード!」と叫んで指示してから、サブマシンガンを投げ捨て、マイナの正面に立って光剣(ライトセーバー)を展開。直前に引き金が引かれていたレーザー・ライフルから射出された光線は、ライトセーバーの前で消滅する。
『わかっているな』
俺とスザクの心境は、同じだったろう。お互い、考えは同じだ。電磁波を『固めた』ライトセーバーは、大抵のエネルギー武器や低威力の実体弾を無効化する。今回はたまたま、いわゆるジャストガードとなった。実際、防御範囲は刀身部分より広めで、バリア効果もあるのだ。
ライフルを持ったまま、今度はもう一方の左手で、腰から大振りの拳銃に似たなにかを取り出すスザク。
――単装式の、グレネード・ランチャーだ。お互いの危険距離でスザクは引き金を引き、即座に正面にバリアを展開。
うわー、せせこましい!
着弾。
俺の手前で、ポン、と射出され、山なりの弾道を小さく描いた擲弾(てきだん)が炸裂。
ライトセーバーの防御効果で、幾分か爆発の威力は減殺された。死んではいないが、追撃を受ければ、まずい。
「この!」
機関銃を後ろで構えたマイナのフルオート射撃は、全てスザクの指向性シールドによって阻まれる。
弾が切れたのを確認しーースザクは電磁式ステルス迷彩を起動。全身が周囲と一体化する。
『撤退だ』
スザクと俺は、なにやら同じ台詞(せりふ)を言ったか、思っていたのかもしれない。
直後にフラッシュバンが投げ込まれーー俺達は背を向けてその場から全速力で逃げだす!
無事帰還するまで、俺はなかなか、生きた心地がしなかった。マイナも同じようなもののはずだろうな。
「あー、楽しかった」、というのは強がりであると同時に、本音だったが……。
微妙に怯えているマイナには、「これ、絶対に良い思い出になるから、な?」と言い聞かせ、無理やり頷(うなず)かせた。
あとがき
次の第三章はスザクを主役に据えた、三人称(視点)小説になる予定です。
第二章までで、構想の全体の、3割~4割弱くらいの文章量かな?
Web小説家の気楽さで、ゆっくり良いものを書いていきたいですね!
ありがとうございました!!
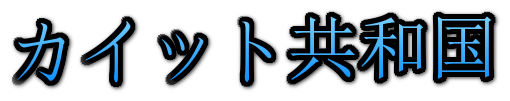

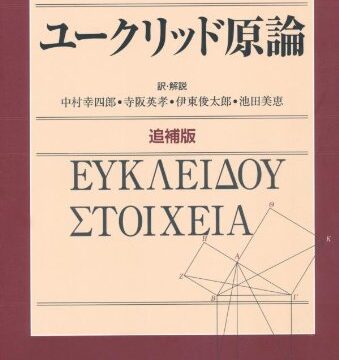




























-320x87.png)